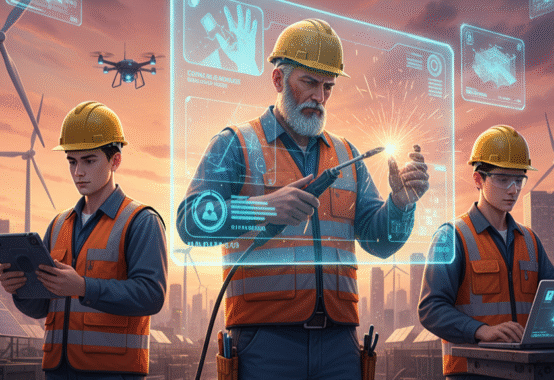建設業界は今、大きな転換期を迎えています。長年続く人手不足に加え、2024年4月にはいよいよ「働き方改革関連法」による時間外労働の上限規制が適用され「2024年問題」が現実のものとなりました。残業時間の削減や週休2日の確保など、これまで慣れ親しんだ業務慣行からの脱却が急務となっています。
現場の第一線で奮闘する建設現場の方々にとっても、この変化は避けられないものです。人員の確保が難しくなる中で、どのようにして生産性を維持し、さらには向上させていくのか。増え続ける業務負担にどう立ち向かうのか。課題を克服するために注目されているのが「建設DX」です。本記事では「建設DX」が必要な理由を深掘りし、人手不足と2024年問題という2つの大きな壁を乗り越えるための具体的な戦略を、現場の視点から詳しく解説します。
目次

1. 建設業界が直面する喫緊の課題:人手不足と2024年問題の深刻化
建設業界は長らく労働力不足の課題に直面しています。少子高齢化により若年層の入職者減少、ベテラン技術者の高齢化と引退が相まって、技能継承の危機が叫ばれています。
追い打ちをかけるのが「2024年問題」です。時間外労働の上限規制が建設業にも適用されることで、従来の長時間労働に頼った働き方は維持できません。建設業界全体の生産性や収益性に大きな影響を与え始めています。
働き方改革と残業規制強化、限られた時間のなかで業務を済ませる
2024年4月1日より、建設業においても時間外労働の上限規制が本格的に適用されました。原則として月45時間、年360時間を超える残業は認められません。特別な事情がある場合でも、年720時間以内、複数月平均80時間以内、単月100時間未満の制限があります。
現場にもスケジュール管理や工程の見直し、人員配置など、あらゆる側面に影響を及ぼします。週休2日の確保も推進される中で、これまで通りの業務量をいかに効率良くこなすかが、企業の存続を左右する喫緊の課題となっています。
若年層の入職者減少とベテラン技術者の引退
建設業界は、全産業の中でも高齢化が特に進んでいます。業界全体の技術レベルの低下や、安全性の確保にも直結する深刻な問題です。建設現場の魅力が十分に伝わっていないこと、過酷な労働条件というイメージが根強いことなども、若者の業界離れの一因と考えられます。新たな担い手の確保と育成は、持続可能な発展のためには不可欠です。
現場管理者・ダンプ事業者の業務負担大、アナログな手法にでは限界がある
「2024年問題」が迫る中、最もその影響を受けるのが、現場の最前線で指揮を執る現場管理者です。限られた時間の中で、これまで以上の成果を求められ、施工管理、安全管理、品質管理、労務管理といった多岐にわたる業務を効率的にこなさなければなりません。
また、現場を支えるダンプ事業者も、労働時間規制に加え、燃料費の高騰や車両手配の難しさ、複雑な書類作成など多くの課題に直面しています。入退場管理や過積載対策、配車計画の最適化などは、アナログな手法では限界があります。
2. 建設DXがもたらす変革:人手不足解消と生産性向上の具体策
建設DX(デジタルトランスフォーメーション)は、デジタル技術を導入することで、建設業界のビジネスモデルや業務プロセスそのものを変革する取り組みです。
単にITツールを導入するだけでなく、働き方までも変えることを目指します。人手不足や2024年問題という差し迫った課題に対し、DXは抜本的な解決策となりえます。属人化していた業務の標準化、データに基づく意思決定の促進、現場の生産性向上が考えられます。
デジタルツールによる施工管理の効率化と業務負担の軽減
「施工管理アプリ」やクラウドの「プロジェクト管理ツール」を導入することで、現場の状況をリアルタイムで共有し、進捗管理、工程管理、資材管理などを一元的に行えます。Excelなどを用いた手作業による集計や報告書作成の手間を大幅に削減できます。
写真や図面をクラウド上で管理することで、関係者間での情報共有がスムーズになり、手戻りの防止や意思決定の迅速化につながります。また、原価管理システムを導入すれば、材料費や労務費を正確に把握し、予算と実績を比較することで、利益率の改善にも貢献します。
スマートデバイスを活用した安全管理・品質確保の強化
タブレットやスマートフォンといったスマートデバイスは、建設現場の安全管理と品質確保において大きな力を発揮します。
例えば、安全パトロールの結果をその場で記録し、ヒヤリハット事例を写真付きで報告できるアプリがあります。リスクの早期発見と共有ができます。また、KY活動(危険予知活動)もアプリ上で行えば、参加者の意識向上にも繋がります。
品質面では、配筋検査やコンクリート打設の管理において、スマートフォンで撮影した写真を自動で整理・分類し、検査記録と紐付けできるアプリが普及しています。書類作成の手間を省きながら、検査の精度と信頼性を高めることができます。
情報共有の高度化とベテラン技術の継承
建設現場における情報管理の課題は、数多く存在します。
紙媒体での情報共有はタイムラグが生じやすく、情報の散逸や誤解を招く原因にもなります。クラウド型の情報共有ツールや図面管理アプリを活用することで、最新の図面や資料をどこからでも確認できるようになり、連絡ミスや手戻りを削減します。
ベテラン技術者の持つ知識やノウハウを、動画やデジタルマニュアルとして記録し、共有する「技能承継DX」も進んでいます。経験の浅い若手でも、質の高い情報を効率的に学ぶことができ、人材育成のスピードアップと技術力の底上げが期待できます。
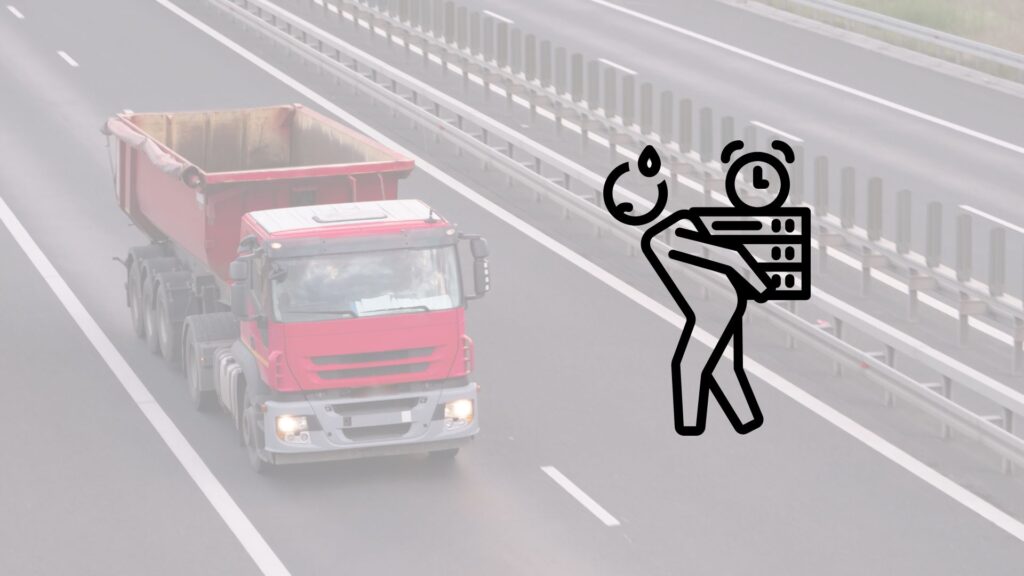
3. ダンプ事業者に必要なDX:運行管理と過積載対策の最適化
建設現場の円滑な進行に不可欠なダンプ運送も、DXによって大きく変革を遂げようとしています。人手不足や燃料費の高騰といった課題に加え、「2024年問題」はダンプ事業者にも労働時間の制約として影響があります。運行管理の効率化、安全性の向上、コスト削減を実現するためには、アナログな管理からデジタル技術を積極的に導入することが不可欠だと考えます。
リアルタイム運行管理と効率的な車両手配
GPS機能を搭載した運行管理システムや専用アプリを導入することで、ダンプの現在地、走行履歴、稼働状況などをリアルタイムで把握できます。現場からの急な依頼にも迅速に対応できるほか、渋滞情報などを考慮した最適なルート選定が可能になり、燃料費の削減にも繋がります。
また、車両の空き状況やドライバーの稼働状況をデジタルで一元管理することで、効率的な配車計画を立てやすくなります。特に、4点セット(運転免許証、運行管理者資格者証、車両台帳、定期点検記録簿)の収集・共有や車両一覧表の作成もシステム上で行えるようになれば、下請ダンプ事業者の事務負担を大幅に軽減できます。
重量計後付けによる過積載防止と法規制への対応
過積載は交通事故のリスクを高めるだけでなく、道路の損傷や排ガス増加など環境への悪影響も大きく、厳しく罰則が科せられます。既存のダンプ車両に後付けできる重量計を導入することで、積載量を正確に把握し、過積載を未然に防ぐことができます。
リアルタイムで運転席から積載状況を確認できるシステムや、積載量が規定を超過した場合にアラートを出す機能などがあれば、ドライバーの意識向上にも繋がり、法令遵守を徹底できます。これにより、罰則のリスクを回避し、安全運行を確保することはもちろん、車両への負担軽減にも繋がり、維持管理コストの削減にも貢献します。
4. どのようにあ効率よく効果的にDXを進めればよいか
建設DXの導入は、単に最新ツールを導入すれば良いというものではありません。企業の文化、現場の状況、従業員のスキルレベルなど、様々な要素を考慮したアプローチが必要です。
中小企業にとっては、大きい投資は現実的ではない場合も多いため、いかに効率的かつ効果的にDXを進めるかが成功の鍵となります。従業員の理解と協力も欠かせません。長期的に見ると、DXは企業成長の強力なエンジンとなるでしょう。
スモールスタートと段階的導入でリスクを最小化
まずは小さく始めて成功体験を積み重ねてみませんか。特定の現場や部署で試験的に導入し、効果を検証してから全体に展開する「スモールスタート」が有効です。初期投資を抑え、リスクを最小限に抑えながら、従業員の抵抗感も和らげることができます。
段階的な導入を行うと、現場の意見を取り入れながら改善を重ねられます。失敗事例からも学べますね。
現場に合ったツール選定と運用サポートの重要性
どんな高機能なツールでも、現場のニーズに合っていなければ形骸化してしまいます。ツールの選定においては、現場の作業員や管理者が使いやすいか、既存の業務フローにスムーズに組み込めるかを考えてみましょう。
多機能すぎて使いこなせない、操作が複雑で浸透しないといった失敗例も少なくありません。導入後も、使い方に関する研修や定期的なフォローアップ、疑問点を解決するサポートがあると安心ですね。
DX推進のハードルを下げる補助金・助成金活用
建設DXの導入にはお金がかかるんでしょう?と思われる方もいらっしゃると思います。国や自治体は、建設業の生産性向上や働き方改革を後押しするため、様々な補助金や助成金制度を設けています。「ものづくり補助金」「IT導入補助金」「事業再構築補助金」など、自社のDX計画に合致する制度を探し、積極的に活用することで、導入費用を大幅に抑えられます。
BIM/CIMやドローン測量、ICT施工などの先進技術の導入に対しても、積算要領の改定や補助金が用意されている場合があります。
5. 未来を築く建設業へ:DXが拓く新たな可能性
ICT施工の進化やi-Construction 2.0といった国の施策とも連動し、データに基づいた意思決定が標準となる時代が目の前に来ています。
DXによる建設現場のスマート化と競争力の強化
建設DXの究極の目標は、建設現場の「スマート化」です。BIM/CIM(Building Information Modeling/Construction Information Modeling)の導入によって、設計から施工、維持管理までを一貫して3Dモデルで管理することもできます。また、ドローンでの測量や進捗管理、IoTセンサーによる現場の状況把握などは、作業の安全性向上と精度向上に繋がるでしょう。
技術を組み合わせることで、結果として企業の競争力強化に繋がります。i-Construction 2.0などの国の推進する施策も、このスマート化を後押ししています。
DXで建設業界は「選ばれる業界」へ
建設DXは、若年層の業界離れを食い止め、新たな担い手を呼び込むための強力なツールでもあります。デジタル技術の導入は、従来の「きつい、汚い、危険」といった”3K”のイメージを払拭できる可能性があります。ドローン操作や3Dモデリング、データ分析は、クリエイティブで魅力的な仕事になると思いませんか。
まとめ:2024年問題と人手不足を乗り越え、未来を築く建設DX
建設業界が直面する人手不足と2024年問題は、待ったなしの喫緊の課題です。同時に、業界全体の変革を促す大きなチャンスでもあります。これを機に、DXを仕事にどう取り入れるかが、業界内でも差がつく部分になります。今こそ、第一歩を踏み出しませんか。
「ミカタシステム」では建設DXにつながるツールを開発しています。まずはお気軽にご相談ください。