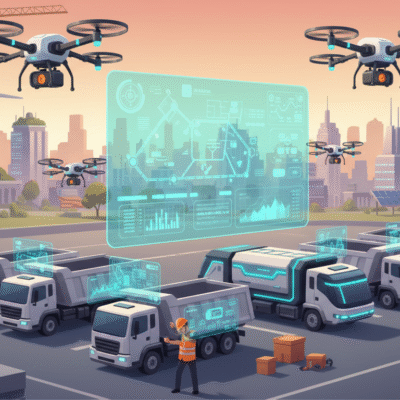建設業界は今、かつてないほどの変革の波に直面しています。長年の課題である人手不足に加え、2024年4月からは「働き方改革関連法」による時間外労働の上限規制がいよいよ本格的に適用されました。「2024年問題」で建設現場の働き方は根本から見直すことを求められており、慣行に甘んじることはできません。
この状況を打開するのが「ICT(情報通信技術)」の活用です。ICTはコンピュータを使った情報処理や通信技術の総称です。
本記事では、2024年問題が建設業界にどのような影響をもたらすのかを掘り下げ、ICTがどのように生産性向上に使えるのかを解説します。記事後半では、残業規制に対応するためのICT活用策5選をご紹介。導入を成功させるための実践的なポイントまで、現場で働く方々にとって役立つ情報をお届けします。
目次
1. 迫り来る2024年問題:建設業界の未来を左右する時間外労働規制の波
建設業界は、他の産業に比べて時間外労働が常態化している傾向にあります。2024年4月以降、この状況は大きく変わります。働き方改革関連法で、建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、現場の運用は抜本的な見直しを迫られています。
建設業の働き方改革の現状と課題
建設業は納期厳守や、天候不順や予期せぬトラブルなどにより、長時間労働が発生しやすい構造にありました。「頑張り」で乗り越えてきた側面も少なくありません。しかし現代社会では、長時間労働は過労死や健康問題を引き起こすだけでなく、ワークライフバランスを重視する若年層からの敬遠にも繋がっています。
働き方改革は、旧来の慣習を見直し、従業員が健康的に働ける環境を整備することを目的としています。大きな社会の流れに逆らうことは、企業としては難しいかもしれません。
残業時間上限規制に対応するのが、生き残りの条件
2024年4月1日からは建設業においても、原則として月45時間、年360時間の時間外労働の上限が課せられます。特別な事情がある場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内、単月100時間未満の制限があり、超過すると罰則の対象となります。
従来の働き方を前提とした工程計画や人員配置では、納期遵守が困難になることが考えられます。対応していくことが、企業の生き残りのための条件となるでしょう。
人材流出を防ぎ、若手を惹きつけるために
建設業界の高齢化は深刻です。熟練技術者の引退が進む一方で、若年層の入職者は減少傾向にあります。「2024年問題」による労働環境の変化は、既存の従業員の離職を招くリスクもはらんでいます。若者が魅力を感じる業界へと変わらければ、労働力不足はさらに深刻化するでしょう。
ICTを活用した新しい建設現場の姿を見せることは、若手人材の確保と定着には不可欠だと考えられます。

2. なぜ今、ICTが建設業界の救世主となるのか?
ICT(情報通信技術)は、建設業界が抱える課題を解決する重要な鍵です。便利なツールを導入したからOKではなく、ICTを戦略的に活用することで「建設DX(デジタルトランスフォーメーション)」へと繋げることができます。
ICT活用の本質は、情報技術を通じて業務プロセスを最適化すること
ICT活用とは、パソコンやスマートフォンを導入することではありません。その本質は、情報技術を通じて業務プロセスを最適化することです。現場の情報をリアルタイムで共有することで、意思決定が早くなり、手戻りを減らします。またデータに基づいた分析は、より精度の高い予測や計画を立てることが可能になり、非効率な作業を無くします。従業員は浮いた時間を、別の業務に集中できるようになるので、コスト削減だけでなく、新たな収益源を生み出すことも期待できます。
属人化から抜け出す
現場では経験豊富なベテランに業務が集中し、知識やノウハウが属人化しているケースが少なくありません。属人化すると、担当者の不在時に業務が滞る原因となったり、若手への技術継承が難しくなります。
ICTを導入することで、現場の状況、進捗、課題、ノウハウをデジタルデータで蓄積し、クラウド上で共有することができます。誰でも必要な情報にアクセスできるようになり、属人化から脱却できます。特定の個人に依存しない、組織全体としての生産性向上とリスク管理の強化が図れるでしょう。
労働時間削減と生産性向上を両立させる秘密
2024年問題への対応として、重要なのは限られた労働時間の中でいかに生産性を高めるかという点です。ICTはその両方を叶えるものです。これまで手作業で行っていた報告書作成やデータ入力、図面の修正といった事務作業を自動化・効率化することで、現場作業員の負担を軽減し、残業時間を削減できます。データ分析を通じて非効率な工程を特定し改善することで、作業全体の無駄をなくし、効率的な施工体制を構築できるようになるでしょう。
3. 残業規制に対応する生産性向上:ICT活用具体策5選
2024年問題に対応し、残業時間を削減しながら生産性を向上させるためには、具体的なICTツールの導入と活用が不可欠です。ここでは、建設現場と管理部門の両方で効果を発揮する5つの主要なICT活用策を詳しくご紹介します。
施工管理アプリで現場業務を効率化
施工管理アプリは、現場の進捗管理、写真管理、図面管理、検査記録、日報作成など、多岐にわたる現場業務を一元化し、スマートフォンやタブレットで手軽に行えるようにするツールです。事務所に戻ってからの事務作業…大変ですよね。撮影した現場写真を直接アプリにアップロードし、工程や場所と紐づけることで、情報の整理や報告書作成の手間が省けます。チャット機能を通じて、現場と事務所、協力会社間での情報共有もスムーズになり、コミュニケーション不足も起こりません。
BIM/CIM導入で設計・施工の手戻り削減
BIM/CIM(Building Information Modeling/Construction Information Modeling)は、建物の設計から施工、維持管理に至るまでの全プロセスを、3Dモデルと連携し一元管理するシステムです。設計段階での干渉チェックや施工シミュレーションができ、手戻りの発生を削減できます。従来の2次元図面では気づきにくかった問題点を早く発見し、設計変更の回数を減らすことができます。施工段階でも、BIM/CIMモデルを活用して資材の数量を自動算出したり、施工手順を可視化したりすることで作業の精度と効率が上がります。
ドローン・IoTを活用した測量・進捗管理の自動化
ドローン技術は、建設現場の測量や進捗管理に新しい風をおこしました。広大な敷地の測量を短時間で高精度に行えるだけでなく、工事の進捗状況を空撮で定期的に記録し、3Dデータ化することで、現況と設計モデルの比較が容易になります。
現場に足を運ぶ回数を減らせて、移動時間も短縮。IoT(モノのインターネット)センサーを建機や資材に設置することで、稼働状況や在庫量をリアルタイムで把握することも。センサーで土量や運搬量を自動計測し、過積載の防止や最適なダンプ配車計画の策定に役立てるのもできます。
クラウド型情報共有ツールで図面・写真管理
建設現場では、日々膨大な量の図面や写真が撮影されます。情報を管理し、関係者間で共有できることはプロジェクトの成否に直結するのではないでしょうか。たとえば、クラウド型情報共有ツールを導入することで、最新の図面や資料、現場写真をクラウド上に保管し、インターネット環境があればどこからでもアクセスできるようになります。
紙媒体での図面持ち運びや、USBメモリでのデータ受け渡しといった手間が不要になること。古い図面での施工や、写真の探し出しに時間を費やすといった無駄をなくして常に最新の情報に基づいた作業ができること。災害時などでも情報のバックアップが取れていることなどが、考えられます。
勤怠管理システムと連携して労務管理をしっかり行う
労働時間の正確な把握と管理は、基本的ながら重要な要素です。たとえば、クラウド型の勤怠管理システムを導入すると、スマートフォン・タブレット・ICカードで従業員の出退勤時間を正確に記録し、労働時間を自動で集計できます。
手書きのタイムカードやExcelでの集計作業がいらなくなり、管理者の事務負担を軽減します。システム上で残業時間の上限に近づいた従業員にアラートを出す機能があれば、過重労働を未然に防ぎ、法令遵守を徹底できます。給与計算システムとの連携も容易になるため、経理処理も楽になりますね。

4. ICT導入を成功させるためのロードマップと注意点
ICTの導入は、建設業界に大きなメリットがありますが、その”成功”は準備と運用にかかっています。ツールを導入しただけでは十分に期待する効果を得られません。
現場の特性を理解して、従業員の協力を得ながら、段階的に進めることが大切です。国や自治体が提供する補助金制度を賢く活用することも、導入のハードルを下げる上で見逃せないポイントです。
スモールスタートと、現場の声を取り入れたツール選び
ICT導入の大きな失敗原因の一つに、現場の状況やニーズを考慮せず、一度に大規模なシステムを導入しようとすることがあります。まずは、小さなものを試験的に導入する「スモールスタート」を検討しましょう。初期投資を抑え、リスクを最小限に抑えながら、ツールの有効性や現場での使い勝手を検証できます。
何より、実際にツールを使用する現場の作業員や管理者の声に耳を傾けることです。意見を反映させながらツールを選び、改善を重ねていくことで、導入後の運用定着率が格段に向上します。
従業員への教育・研修と運用定着の秘訣
新しいICTツールを導入しても、従業員が使いこなせなければ意味がありません。ツールの使い方に関する丁寧な教育・研修は不可欠です。特に、ITリテラシーに差がある可能性も考慮し、それぞれのレベルに合わせた研修プログラムを用意することが望ましいでしょう。
成功の秘訣はツールを使うことのメリットを理解してもらい、「これを使えば楽になる」と実感を持ってもらうことです。社内で成功事例をシェアしたり、キーパーソンを配置することも、運用定着を促します。
補助金・助成金を活用した賢い投資戦略
ICTツールの導入には、初期費用やランニングコストが発生します。国や地方自治体は、建設業の生産性向上や働き方改革、DX推進を支援するための様々な補助金・助成金制度を提供しています。代表的なのは「IT導入補助金」や「ものづくり補助金」、「事業再構築補助金」などですね。上手に活用することで企業の負担を軽くできます。
まとめ:ICTで2024年問題の壁を乗り越え、未来を切り拓く建設業へ
建設業界にとって、人手不足と2024年問題は避けて通れない大きな課題です。でも業界全体を変え、見直す機会でもあります。
本記事でご紹介した施工管理アプリ、BIM/CIM、ドローン・IoT、クラウド型情報共有ツール、勤怠管理システムといったICT活用策は、あくまで一例です。2024年問題という大きな壁は皆んな同じ状況なので、一緒に乗り越えていきましょう。
「ミカタシステム」では建設DXにつながるツールを開発しています。まずはお気軽にご相談ください。